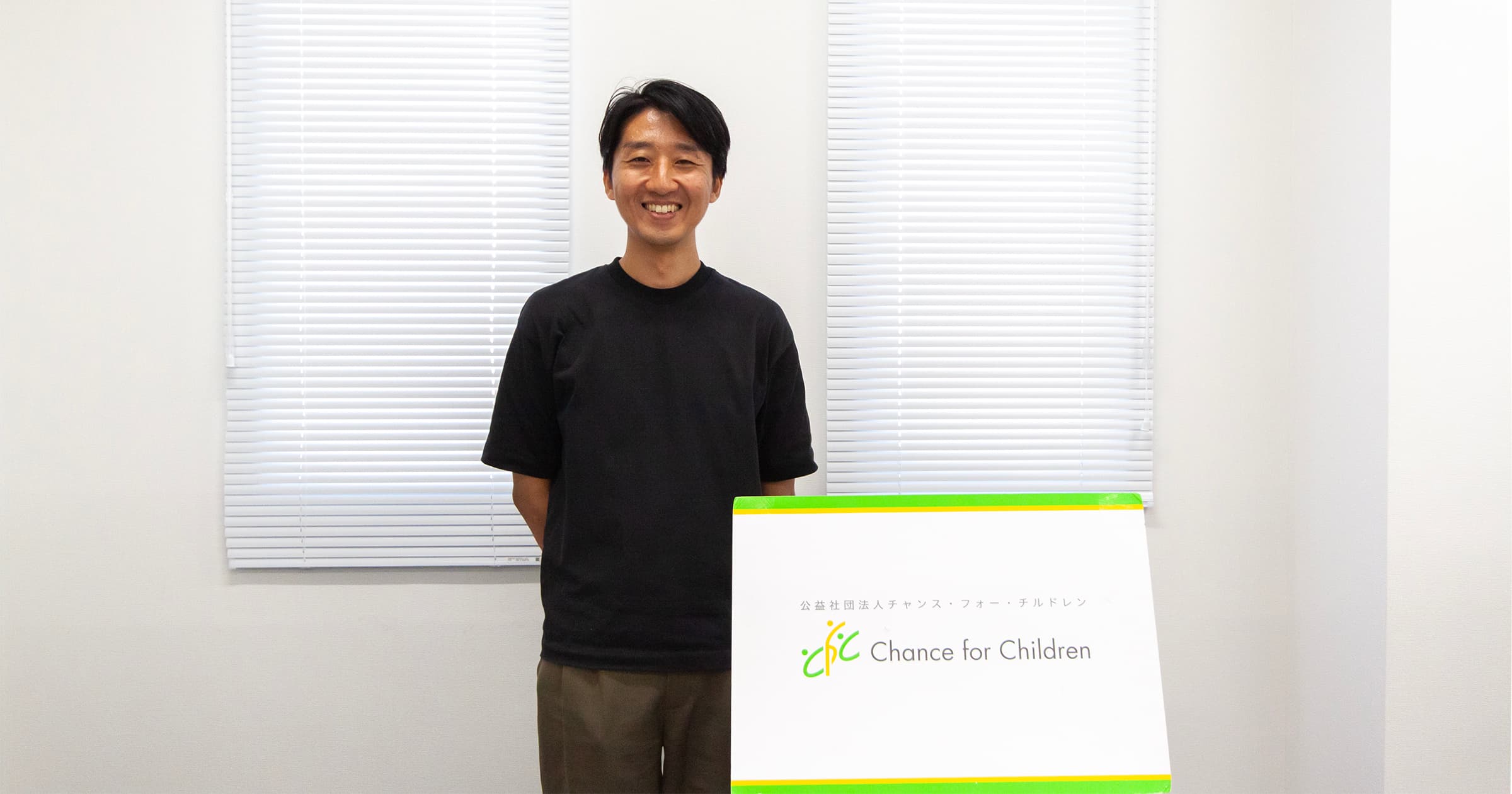
チャンス・フォー・チルドレン(後編) 代表理事 今井悠介さん
貧困の世代間連鎖を断ち切るべく、子どもの学習・体験機会の格差解消に取り組んでいる公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン。同法人代表理事の今井悠介さんへのインタビュー後編では、活動のなかで出会った方々とのエピソードやこどもふるさと便への期待、子どもたちの学びをめぐる今後についてうかがいました。
支援を受けた子どもが支援の担い手に
——これまで子どもたちに学習・体験機会を提供する活動をされてきたなかで、子どもたちや協力先の事業者の方々とのエピソードで印象に残っていることはありますか?
スタディクーポンを利用した子どもたちのなかから、次の世代の子どもたちを支える担い手が育つことです。たとえば、大学生になって学生ボランティアとして関わってくれる子もいれば、社会人になって収入の一部を寄付してくれる子もいます。なかには自ら塾を立ち上げ、その塾をスタディクーポンの利用先として登録してくれる子もいます。
このように、時間の経過とともに同じ人でも関わり方は変わってきます。ときには、寄付や支援をする側だった人が、支援を受ける側に回ることもあるでしょう。社会とは、みんながどう支え合えるかという営みだと考えています。だからこそ、その時々の状況に応じて、互いにさまざまな役割を担い合える社会でありたいと願っています。

——スタディクーポンやハロカル奨学金の利用先として、子どもたちに学習や体験の機会を提供する事業者からのフィードバックで、何か印象的だったことはありますか?
ハロカル奨学金の利用先として登録してくださっているある音楽教室の先生から、「この活動は私の夢でした」と言われたことが印象に残っています。その先生は、自分が得意な音楽をいろいろな子どもたちに届けられる教室をつくりたいと思って教室をはじめました。けれども、ご自身の子育てを含めていろいろなご苦労があって、月数千円の月謝を払える家庭の子にしか教えられなかったらしいのです。
ハロカル奨学金の仕組みを使えば、月謝を払うことができない家庭の子どもたちにも音楽体験を届けられる。「まさにこういう活動をしたかったんです」といって参加してくださったんです。これを教えていただいたときは、すごく嬉しかったのを今でも覚えています。
音楽でもスポーツでも、自然体験でも、大好きなことを本気でやっている大人に子どもたちが出会えることも大事だと思っています。たとえば、私も学生時代のワークキャンプに子どもたちを引率する活動のなかで、脱サラしてマレーシアに渡り、現地で植林の指導者になった人と出会いました。そのような人と一緒に植林活動をしていると、何か言葉には言い表せない感じるものがあります。
ここまで極端ではなくても、自分はこれが好きだというものに対して、プライドをもって真剣に取り組んでいる人たちが地域のなかにたくさんいます。そういう人たちと一緒に過ごす時間をもつことによって、長期的に考えれば、すごく大事な何かが子どもたちのなかに残っていくのではないかと考えています。

地域のつながりと情報へのアクセス
——体験を提供するということは、単に楽しい体験をしてもらうだけでなく、体験を通じた人との出会いや新しい価値観との出会いをつくることにもつながっているのですね。さきほど、経済格差と体験機会の関係をうかがいましたが(※前編参照)、人との出会いについても経済格差の影響はあるのでしょうか?
おっしゃるように、体験は社会関係資本(他者とのつながり)とすごく関係が深いといわれています。
習い事や旅行・キャンプなど、一般的にお金がかかるイメージのある活動において、家庭の経済状況による格差があることは、感覚的に分かりやすいかと思います。でも実は、私たちがおこなった調査の結果からは、安価または無料で参加できるような地域の行事やお祭りに参加する機会も、家庭の経済状況で差が生じていることが分かりました。
地域のクラブ活動もそうだし、お祭りや行事など、地域のなかにある体験の情報は、必ずしもどこかにまとまっているわけではありません。人づてに知ることも多く、地域のネットワークにつながっていれば自然と情報が入ってきますが、そうでないとそもそも情報を得ることができません。
経済的に苦しい家庭の話を聞くと、地域から孤立していることがよくありますが、こうした家庭に経済的な支援だけを届けても、上手く地域の体験の場につながっていけないことがあります。
そのような背景から、ハロカルでは子どもや家庭が体験を通じて地域コミュニティとの関係性を紡いでいけるように意識しながら伴走しています。
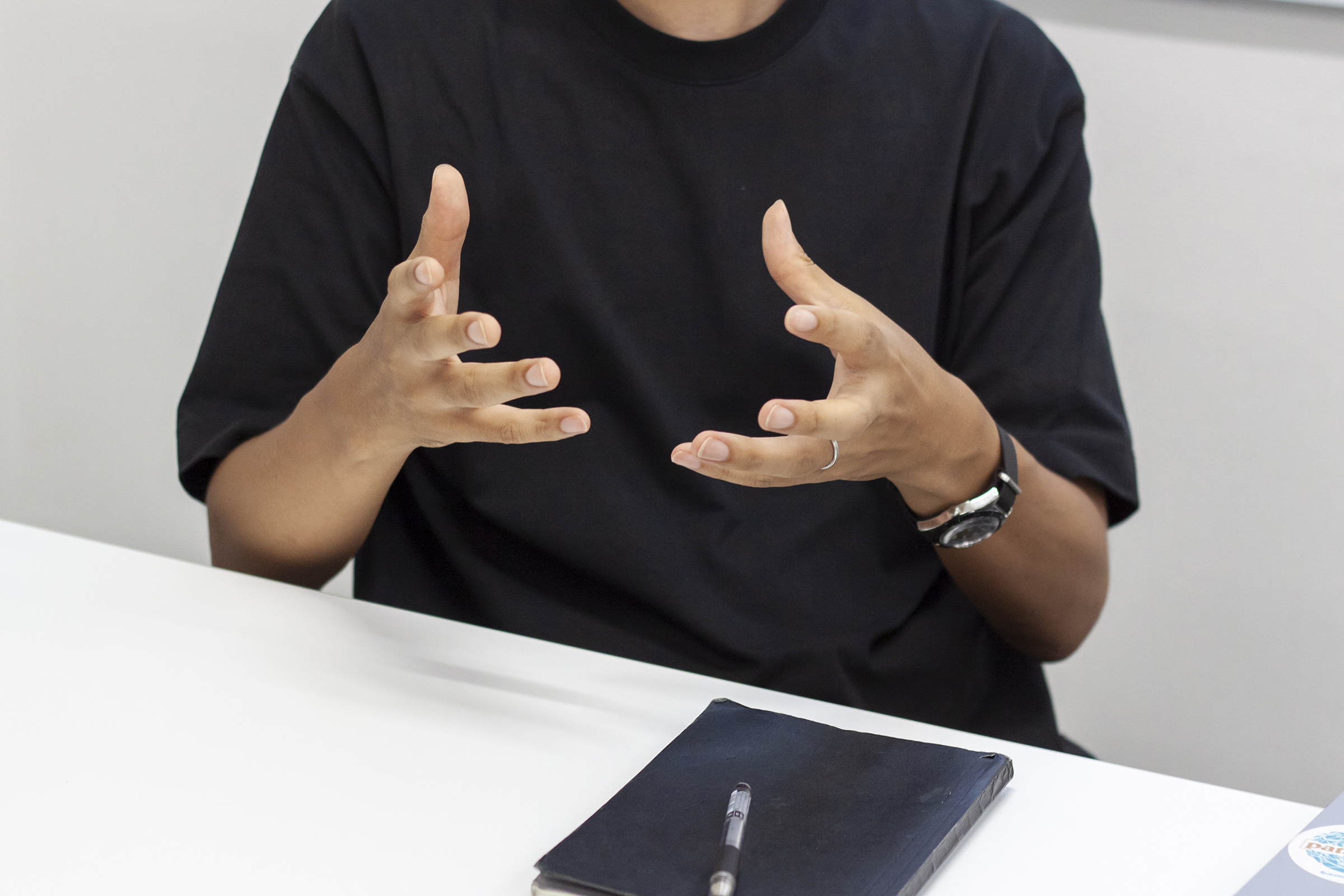
こどもふるさと便と連携することでできること
——今回、こどもふるさと便に参加してくださることで、チャンス・フォー・チルドレンを通じて経済困窮家庭の子どもたちに支援を届けられることになりました。参加を決められた背景には、どのようなものがあったか教えていただけますか?
こどもふるさと便を利用させていただくことで、私たちがこれまでできなかったことができると思いました。
これまで子どもの学びや体験の話をしてきましたが、そのベースには日常生活の安定があると認識しています。加えて、昨今の物価高騰の状況下においては、それまでも十分だったとはいえない食費を削りながら、なんとか生活している家庭も多く、実際にそのような声をご家庭からいただくこともあります。
時々、企業などからご案内をいただいて、私たちが支援する家庭に対し食糧支援の制度を告知することもありますが、そのような情報に対して手を挙げる方はすごく多いです。それだけ日々の生活に困っている子育て家庭がたくさんあることを実感しています。
私たちも食の支援の必要性は強く感じているものの、現状では学びや体験の支援に精一杯で、それでもなお必要とするすべての子どもたちに支援を届けきれていません。そのようななかでは、なかなか自分たちの事業として食の支援にまで手を広げられないのが実情です。ですが、こどもふるさと便と連携できれば、私たちがつながっている家庭が抱える食の問題に対してもアプローチできます。それが、参加を決めた大きな理由です。
——こどもふるさと便では、まずは食品を子どもたちに届けることが決まっていますが、それ以外にこういうものが子どもたちに届けられたらいいなというものはありますか?
いろいろな体験機会にもつなげていけるといいなと思っています。たとえば子どもたちが地域のスポーツや音楽の活動をしていても、用具の問題が出てくることがあります。たとえばサッカーをするためのスパイクがないといった問題が実際に起こっています。
参加するための費用は私たちの活動でサポートできますが、それ以外の用具や楽器、会場施設などの費用面の問題についても、こどもふるさと便の仕組みで解消することができるかもしれない。そうなると子どもたちができる体験の幅もさらに広がっていくと思いました。
活動をしていると、目の前にはニーズがたくさんあることが分かりますが、自分たちだけではどうしても限界があります。すごくジレンマがあるわけですが、こどもふるさと便のような連携や協力の仕組みがあると、可能性が広がると思います。

子どもたちに体験機会をもたらす地域のエコシステム
——人口減少や地域コミュニティの希薄化にともなうさまざまな問題が地域で顕在化していますし、その流れは加速していくことが予想されます。そういったなかで、子どもたちの体験を取り巻く環境についてどうお考えでしょうか?
これまでの流れでは、子どもたちの体験活動は地域に支えられてきた部分が大きいと思います。町内会や子ども会、あるいは地域のスポーツクラブなど、そのような場を通じて、地域の人たちが体験活動の機会づくりを担ってくれていました。
しかし、そうした地域の関係性のなかで成り立っていたものが社会の変化によってどんどん弱くなってきています。こうした地域の受け皿が小さくなるにつれて、体験機会の確保が、より各家庭の裁量や経済的な状況に左右されやすくなっているように思います。
もちろん、子どもたちが日々のなかで得る学びや、お金をかけずにできる豊かな体験は何物にも代えがたい貴重なものです。
とはいえ、家庭の経済的な状況によって、子どもたちがアクセスできる体験の「種類」や「選択肢の幅」に差が生まれてしまうことも懸念されます。たとえば、本人の興味や関心をさらに専門的に深めていくような学びや、多様な文化にふれる機会など、経済的な基盤があることで得やすくなる体験も少なくありません。
そうした機会にふれることなく育つ子どもたちが増えてしまうと、一人ひとりが持つ本来の可能性を十分に広げられないようになってしまうかもしれません。
一方で、さきほどの音楽教室の先生のように、地域のなかにも子どもたちのために何かしたい大人はいます。しかし、機会がなかったり、どうやったら子どもにアプローチできるか分からなかったりします。
だからこそ、子どもたちのために何かやりたいと思っている人たちが一歩踏みだすきっかけがあったり、スタディクーポンやハロカル奨学金、こどもふるさと便といった仕組みで体験活動にかかるコストをまかなうことができるようになったりしていけば、より持続可能な形で子どもたちに体験機会を届けることができるのではないかと考えています。

——今後、事業のなかで特に注力していきたいポイントはあるでしょうか?
まだまだ実践の途上だと思っていますが、子どもたちの体験活動の機会を増やしていきたいです。子どもたちがやってみたいけれどできないことをなくすためには、地域のいろいろな人たちとの関係性やエコシステムが大事になります。これらをどうつくっていくかが、私たちの今後の課題だと思っています。
ハロカルでは地域のNPOや行政とも協力しながら事業を進めていますが、仕組みや制度をつくっても、うまく使ってくれる地域の人たちがいないと私たちの事業は成り立ちません。
具体的には、地域で子どもたちの学びや体験にまつわる活動をしているプレイヤーの方々、福祉の分野で困窮者や家庭のさまざまな支援をしている方々とつながっていくことも必要だと考えています。
たとえば食事を提供する支援活動のなかで、「この子がこういう体験の機会があったらやりたいと言っていたな」とか、「この子は来年受験だから勉強したいと言っていたな」というときに、「あの仕組みがあるじゃん」と思い出して使ってくれるような、そういう大人を子どもたちの周囲に増やしていくことにも取り組んでいきたいです。



