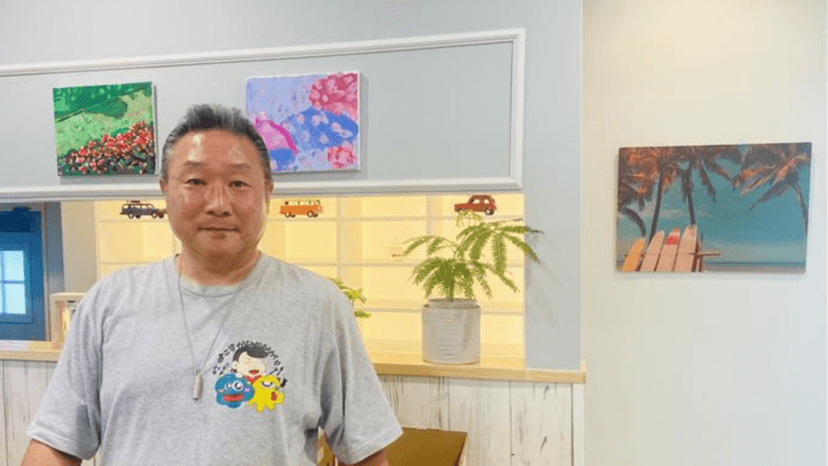D×P(前編) 理事長 今井紀明さん
不登校、いじめ、虐待、家庭内不和、経済的困難、学校中退やそれにともなう無業など、さまざまな理由で孤立してしまう子ども・若者たち。頼れる人とのつながりを失い孤立状態になると、社会にあるセーフティネットにたどり着くことも難しくなり、生活していくうえでもさまざまな困難を抱えることになります。
そんなセーフティネットから抜け落ちやすいユース世代(13歳から25歳の若者)の孤立解消に取り組んでいるのが、認定NPO法人D×P(ディーピー)です。こどもふるさと便で支援を届ける団体のひとつでもある同法人の理事長・今井紀明さんに若者の孤立とその解消にむけた活動についてお話をうかがいました。聞き手は、ネッスー株式会社代表の木戸優起です。
セーフティネットから抜け落ちる子ども・若者たち
——「ユース世代に、セーフティネットと機会提供を」というミッションを掲げ、さまざまなかたちで若者の孤立解消に向けた取り組みをされていますね。具体的な活動内容についてお話いただく前に、まずは若者の孤立という社会課題について教えていただけますか?
D×Pがサポートしているのは、家族や学校、社会とのつながりを失い、孤立している若者たちです。不登校や中退、家庭内不和、経済的困窮など、複数の困難が重なることで、若者たちは自分の居場所を失い、社会から孤立していきます。
調査データをみても、小中高生の不登校や自死、児童虐待の相談件数は、いずれも過去最多となっており、若者の孤立は年々深刻化していることがうかがえます。
——孤独・孤立は、それ自体が大きな問題であり、それによってさまざまな問題が引き起こされることが知られています。孤立の問題にまつわる若者ならではの特徴といえることも、何かあるでしょうか。
まず、未成年の場合 、大人と比べて自力でとれる選択肢は狭くなります。そして、頼れる人とのつながりをなくし孤立した状況になると、自力では社会にあるさまざまなセーフティネットへたどり着くことが難しくなります。孤立によってセーフティネットにつながりづらくなることはほかの世代にも言えることですが、生活が困難だからこそ危険な大人とつながり、それによって事件に巻き込まれてしまうといった深刻な状況に陥ってしまう若者たちもいます。
頼れる人とつながれるかどうかは、自分の居場所だと思える場やコミュニティをどれだけ持っているかにも関係します。そして家庭の経済状況が困難であるほど、教育や文化的経験の機会が少なくなるだけでなく、居場所だと思える場やコミュニティに出会うきっかけが少なくなることが内閣府の調査で分かっています。
くわえて、過去の経験によるつながりづらさもあります。いじめや人間関係のトラブル、家庭での虐待・無関心など、さまざまな背景からくる心理的ハードルです。これらが重なると、さらに孤立が深まります。

オンライン相談と食糧支援が一歩ふみ出すきっかけに
——孤立の問題を抱えた若者たちに対して、どのような活動をされているのでしょうか。
私たちD×Pは、「ユース世代」と呼んでいる13〜25歳の若者の孤立解決に取り組んでいます。行政、NPO、企業など、多くの方々と連携しながら、不登校、中退、経済困窮、社会的孤立といった困難を抱える若者と出会い、寄り添いながら支援を届けています。
——具体的には、どのような事業をおこなっていますか?
困難を抱える全国の若者に向けて、「ユキサキチャット(https://www.dreampossibility.com/whatwedo/yukisakichat/)」というLINE相談と、経済的に厳しい状況にある若者への食糧支援や現金給付をおこなう「ユキサキ支援パック(https://www.dreampossibility.com/whatwedo/project/food-support/)」 を展開しています。ユキサキチャットは、13〜25歳の若者を対象に、生活や進路の悩みなどを気軽に相談できる窓口です。ユキサキ支援パックは、15〜25歳で、親などの保護者に頼ることが難しい若者を対象に、生活困窮に寄り添う支援を届けています。
ユキサキ支援パックでは、「何も食べていない」「1日1食で我慢している」といった声が日々寄せられるなか、必要としている若者たちに、1箱約30食入の食糧を届けています。また、必要に応じて生理用品なども一緒に届けます。
食糧の内容は、お米、パスタ、レトルト食品、缶詰などですが、オンライン面談やオンラインフォームを使ってアレルギーや調理道具の有無を確認し、一人ひとりの状況にあわせて支援内容をカスタマイズしています。「お米をもらっても炊飯器がない」とか、「レトルトのほうがすぐに食べられていい」といった声もよく聞かれます。

画像提供:認定NPO法人D×P
——支援する食糧の内容も一人ひとりにあわせているのですか。
私たちは寄付でいただいたお金を使って食糧を購入し、できるだけ一人ひとりに合った内容に調整しています。そのほうが寄付金を有効に使うことにもつながりますし、受け取る方にも「自分のことを考えてくれている、大切にされている」と感じてもらいやすいと思っています。
それを1回で終わらせるのではなく、3ヵ月、半年、1年というスパンで継続してサポートしていき、誰かがサポートしてくれている、見守ってくれている、ということを感じられる支援のかたちをつくっていくということをやっています。
——見守ってくれる人がいる、と感じられることはとても大切ですね。
ライフラインの滞納の解消・引越し・医療費など、一度に大きな出費がある場合は「緊急支援パック」として現金給付もおこなっています。支援パックを送る場合は、ただ送るだけではなくチャットでの伴走支援も継続しておこないます。「生活を立て直し働き始めた」「勉強に集中でき国立大学に合格できた」といった声もあり、食糧支援や現金給付が彼らの将来の一歩につながるきっかけになっています。
——LINEという気軽に相談できるツールを使うことで、困っている若者とつながり、支援内容をカスタマイズしながら、その人が将来に希望をもてるようにしている。
日本では、福祉分野のオンライン相談というのがかなり限定されてます。しかも、若者の総合相談みたいなかたちが多くて、福祉に特化した相談窓口ではないことが多いです。一方で、若者の側からみると、生活がかなり困窮していて「今日、食べるものがない」とか、そういった緊急性が高い相談ができる窓口が必要とされています。私たちの問題意識としては、国がおこなっていないからこそ、資金を集めて民間でやっていく、そして調査・提言をおこなうことで現状を変えていきたいということを考えています。
——オンライン相談や食糧の支援だけでなく、実際に居場所をつくって対面での支援もおこなっていますよね。
大阪ミナミの繁華街、グリコ看板の下「グリ下」には、DVや虐待などの背景を抱え、居場所を求める子ども・若者たちが集まっています。こうした場所は全国にも点在しており、東京・新宿の「トー横」もそのひとつです。 私たちはグリ下から徒歩5分の場所に「ユースセンター」を開設し、若者が安心して訪れ、食事をとったり、相談ができる居場所をつくっています。センターが開いていない日でも、つながった若者に対しては、医療機関や自治体窓口への同行支援などもおこなっています。
ユースセンターを中継点として、行政や地域の支援団体など、社会にある多様な資源と若者がつながれるようにすることで、一人ひとりが「自分らしく生きられる」ためのセーフティネットを築いていくことを目指しています。

画像提供:認定NPO法人D×P
(後編につづく)